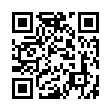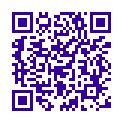2012年11月14日 号(№121)
2012年11月14日 号(№121) ![]()
2012年 霜月しもつき 平成24年、昭和87年、大正101年、明治145年
スカイツリーのシーリング

第22回東シ協技術講習会で、堀長生氏(大林組)が講演
東日本シーリング工事業協組(苅谷純理事長)は、10月25日、東京・アルカディア市ヶ谷で第22回技術講習会開催した。
>つづきを読む
耐火・耐風、外壁の品質向上などへの取り組み報告

社団法人日本金属屋根協会 116回理事会
(社)日本金属屋根協会は10月26日、第116回理事会を開催し平成24年度事業の中間報告を行い、24年度事業として進行中の1.耐風性の研究、2.「金属屋根の施工と管理」の改定、3.新たな屋根30分耐火構造認定の取得と認定内容のなどの進捗状況を確認した。>つづきを読む
建築学会が「陶磁器タイル張り工事」改定で追加講習会

10月26日、日本建築学会「JSS19陶磁器タイル張り工事」改定講習会
前回は180名の定員を大きく上回る参加があり、参加できなかった希望者からの強い要望により、今回の追加講習が実現した。>>全文を読む
絵日記
新着ニュース
2012/11/13 シーリングの性能設計でシンポ![]()
2012/11/13 秋は今日まで。![]()
2012/11/11 鶴川絵日記 茶畑上空![]()
2012/11/09 都市における熱環境に関する最新の研究事例![]()
2012/11/07 むべ 近江神宮に献納![]()
2012/11/04 桧皮葺に銅の樋
2012/11/01 スカイツリーのシーリング
2012/10/31 耐火・耐風、外壁の品質向上などへの取り組み報告
2012/10/29 長月十五日。黒川(多摩)の月
2012/10/29 建築学会が「陶磁器タイル張り工事」改定で追加講習会
2012/10/30 ツタンカーメン展と防水の接点
2012/10/24 少しずつ瓦がのっています
2012/10/23 ライト様式のテラコッタにも触れます
2012/10/23 「霜降」の朝、「武相荘」の森にかかった虹
2012/10/20 深川不動尊の銅板屋根
2012/10/18 樹齢100年の禅寺丸と茅葺き屋根
2012/10/17 防水材料別施工実績(JWMA発表2012年上半期)
2012/10/15 平成24年度 建設マスター顕彰
2012/10/12 UR都市機構 10.30に研究報告会
2012/10/11 秋の銀座 夜の紅葉
2012/10/11 京都府庁旧本館
2012/10/08 伊勢神宮 正殿の茅葺き屋根
2012/10/08 「板金いま、むかし」ルーフネットで転載中。
2012/10/06 屋根が無いから、屋根のことを考える
2012/10/05 正倉院の防水用屋根下ルーフィングはサワラの土居葺
2012/10/04 ツタンカーメンと防水の接点 ③
2012/10/02 平成23年中にサッカーコート 34面分の屋上が緑化整備
2012/10/01 正倉院正倉の校倉(あぜくら)
2012/09/30 「板金いま、むかし」ルーフネットで連載開始。
2012/09/28 十三夜
2012/09/28 正倉院正倉の軒先から東大寺と興福寺を見る
2012/09/26 関東防水管理事業協組総会
2012/09/23 ツタンカーメンと防水の接点 ②
2012/09/23 リフォーム&インテリアショー
2012/09/22 確かに東北新幹線は東京駅からでている
2012/09/20 黄金のマスクより興味深い瀝青の王と女神
2012/09/19 土木研究所 創立90周年記念講演会
2012/09/17 ツタンカーメンと防水の接点 ①
2012/09/16 東京駅ルネサンス
2012/09/15 紫式部色づく
どんぶり勘定。実は懐の深い合理的システムだった。

完成間近の東京駅。ピカピカの銅板が眩しかったですね。(写真は本記事と直接関係はありません)
※ ※ ※
ルーフネット121号連載読み物、今回は明治生まれの銅板屋根職人・鴨下松五郎さんへのインタビュー記録の6回目です。社団法人日本金属屋根協会が機関誌「施工と管理」に連載した記事の転載です。日本金属屋根協会は平成7年から4回にわたって、名高い銅錺師(どうかざりし)鴨下松五郎さんのインタビューを機関誌「施工と管理」に掲載しました。
ヌケた振りした材料の売り手の太っ腹、町場と野丁場の仕事ぶりといがみ合い。「どんぶり勘定」の基本は手間、材料、風袋(ふうたい)=経費。この三つがそれぞれ三分の一ずつ…などなど、粋な人心掌握術がありました。現場の見かけの効率だけを評価する近年のビジネスモデルとは一味もふた味も違う、懐意の深いシステムが現場で機能していた。 なにより驚くのは」鴨下さんの記憶力。 各業界にこういう人が一人はいるようですね。鴨下節引き続き好調です。
板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く- ⑥
坪何枚いるんだい?
当時の屋根の板金工事は今で言う建築金物の業者から私等は受けてましたね。建築金物の業者が屋根の仕事も一緒に受けて、それを板金屋に流してくれる恰好になってました。昔、千住に「おばけ煙突」という4本煙突で有名な建物がありましたが、あれは火力発電所なんです。その火力発電所が千住に移る前に蔵前にありました。蔵前の時は3本煙突だったと思いますが、その屋根の仕事を神田にあった「やまじょう・高田屋」さんが受けて、私等が仕事をやりに行きました。その高田屋さんの人は「あんさく」とみんなに呼ばれてました。「あんさく」って何かって言うと「按摩のさくさん」だと……つまり仕事が見えないというわけです。今なら材料は一坪当たり何枚必要か、ということは仕事を出す方も分かっています。しかし当時は何枚必要かよく分らなかったんです。前にもお話しましたが手間が安かったもんですから、材料を懐に入れちゃってそれで「足らないよ」って言うと、「あんさく」さんはすぐに持ってきてくれたそうです(笑い)。それでも儲かったと言ってた。もっともこれは裏を返せば、太腹で上手に人を使ったということでしょうね。職人さんのほうが「あんさく」だったかもしれません。
もっとも板金屋のほうでも、例えば銅板の屋根です一坪で10枚か11枚あれば葺けるわけです。役物がいるから1枚ぐらいは余計に見ておきますが……、それを「1 枚なければ出来ない」なんて平気で言ってました(笑い)。こんなとぼけたことが通った時代でした。
町場、野丁場
少し大きな仕事になりますと、今より義理堅い世界でしたから「あそこでやってる仕事だから応援しよう」ってことで、非常にうまく仕事をこなしてましたね。当時の町場の板金屋は親父と伜、あと職人か「小僧」が一人か二人という規模がほとんどでした。大きいところで親方を入れて5、6人でしたから、協力し合わないとちょっと大きな仕事になると出来ません。人間が10人いれば、はっきりいって野丁場です。
当時も町場と野丁場の人達はあまり仲が良くありませんでした(笑い)。町場は町場で固まって、野丁場同士で固まって……野丁場の中でも仲のいい人、悪い人がいるって感じでした。町場のほうでは「野丁場なんて奴等は……」って、「かたき」のように思ってましたが、今では私のところも野丁場みたいになっちゃいましたがね(笑い)。
昔も材料の仕入れ値は町場と野丁場は違ってました。私等は5枚、10枚という単位で買っているんですから、彼らとは当然値段が違ってた。ですから町場の業者は大きい屋根……100坪あると大変大きな屋根でしたが……そういう仕事には手が出ませんでした。
「清水」さんに出入りしていた関係で、一度大きな倉庫の仕事をしないかと言われて、見積を入れたことがあります。私としては一番安い手間と材料で計算して出したんですが、野丁場のほうから出て来た値段は、私のほうの材料代だけの価格でした。競争にも何もなりません。それで「いくら贔屓にしてもらっても材料代だけでは出来ません」って、お断りしました。これなんか一つの例ですね。仕事の上手い下手では、はっきりいって町場のほうが上手でしたね。だから町場の人間は野丁場の仕事を見て「こんな仕事をしやがって」なんて言ってました。しかしこれは無理な話しなんでず。野丁場は速く仕事をあげようとしてますから。グズグズした仕事は出来ないわけですから。
どんぶり勘定
見積をする時は、材料とか手間を拾っていくんですが、不思議と「どんぶり勘定」と合っちゃうんです。手間、材料、風袋(ふうたい)ようするに経費ですね。この三つがそれぞれ三分の一ずつというのが、「どんぶり勘定」の基本です。残りの一割は、難しい仕事だと手間に食い、材料の良いものを使うと材料に食いという形になりますから、3割は残さなければいけない、という考え方です。親父なんかも3割は抜かなければいけない、と言ってました。
ですから仕事は「どんぶり勘定」でも大きな間違いは起こらないんです。ただ、使い方が「どんぶり勘定」になると、おかしくなっちゃうんです。仕事での計算は「どんぶり」でも合いますが、使い方が……私生活で「どんぶり」をしたりすると、そういう人はだいたい失敗してますね。仕事を取ったとなると前祝いをしちゃう人もいました(笑い)。儲かるかどうか分からないうちに前祝いという気分になっちゃって、お金を貰えないうちから、道具を買うとか、飲んじゃったりする。それで材料代が払えなくなったりして、いなくなっちゃった人も結構いました。遊びは誰だって面白いわけ。誰だってやりたいんですが、限度がある。限度を超すとお店を仕舞ってどこかに行ってしまうことになる。「あいつは街遊びは上手いけど、仕事はまずい」なんて言われちゃうわけ(笑い)。ですから材料屋さんのほうでも、売掛の枚数を板金屋ごとに細かく決めてました。例えば 0枚しか貸してはいけない板金屋が「 枚必要だ」となると、「お前さん気を付けてくれよ」とはっきり言われます。それだけの用心はしますよ。
そういう人でも腕が良ければ「わたり」職人として生きていけました。3日ばかり稼いで、また次にいくという恰好で日本中を渡って歩いている。彼らは腕はいいです。腕が良くなければ使ってもらえませんからね。腕はいいが身持ちは悪い(笑い)。本当にど
うしょうもない人がいましたね。
うちにも「お隠れ銀次」ってあだ名で呼ばれていた「わたり」職人がいましたが、名前の通りすぐいなくなっちゃうんです。いなくなるだけならいいんですが、ある時「銅金で働いている」と言って相手を信用させておいて、さんざん飲み食いして逃げちゃった。それでまた警察です(笑い)。警察に呼び出されて「お前のところは、どうしてそういう悪い奴ばかりいるんだ」……となる。「どうして」と言われても、それこそ困っちゃいます(笑い)。今から考えるとすごい職人が多かった、というのが実感ですね。
(つづく)
「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。
防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。
- 主な収録項目
特集ページ
- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」
- 燃土燃水献上図を探ねて
- 「聖書と防水」3部作
- 「日本書紀と瀝青」
- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水
- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット
- 「お初」の上七軒だより
- 日本橋改修工事
- 武生余話
- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。