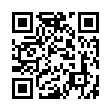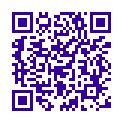防水の不具合は「減らす」から「無くす」へ
防水の不具合は「減らす」から「無くす」へ
2014年建築学会神戸大会の材料施工部門研究協議会
「防水の不具合は‘減らす’から、‘無くす’を目指す」9月13日午後のセッションで

(写真は記事とは関係がありません)
※ ※ ※
9月13日(土)13:30~17:00 神戸大学国際文化学部K601室で。
テーマと担当は次の各氏。
- 司会:輿石直幸 (早稲田大学)
- 副司会:山田人司 (安藤・間)
- 記録:岡本 肇 (竹中工務店)
- 主旨説明:堀 長生 (大林組)
- 主題解説:
- 不具合のない防水設計の考え方:田辺幹夫 (久米設計)
- 防水材料メーカーから見た実態と今後の課題
- メンブレン防水材料:中沢裕二 (日本防水材料連合会)
- シーリング材:伊藤彰彦 (日本シーリング材工業会)
- 防水工事専門業者から見た実態と今後の課題
- メンブレン防水工事:松田健一 (全国防水工事業協会)
- シーリング工事:野口 修 (日本シーリング工事業協同組合連合会)
- 施工管理の実態と今後の課題:名知博司 (清水建設)
- 海外の動向:宮内博之 (建築研究所)
- 討論
- まとめ:田中享二 (東京工業大学名誉教授)
防水は、建築物に要求される「漏水を防止する」という基本的な機能を担っている。本会は、防水工事の品質向上を図るため、『建築工事標準仕様書・同解説 JASS 8 防水工事』や関連する指針等を策定し、より良い建築防水の普及に努力しているところである。
しかし、日常の実務で感じているように万全な防水はそう簡単ではないのが実状である。本研究協議会では、防水工事の実態と課題を共有化したうえで、建築防水の今後のあり方を探る。
言うまでもなく防水工事は、設計者・施工者・専門工事業者・材料メーカーが一体となっての共同作業が重要であるとの認識のもと、設計者から、下地の特性を考慮した防水仕様の選定や防水納まりの留意点など、防水材料メーカーから、不具合発生の要因分析と、「不具合をなくす」にレベルアップするための取り組みの紹介、防水工事専門業者から、不具合の実態と対策について報告するとともに、深刻な技能者不足への対応と技能者育成の取り組みを紹介する。施工者から、品質管理表に基づく工事管理のポイントを紹介するとともに、技能者の質の向上が期待できない状況の中で、プロセス管理法の導入の効果を紹介する。また海外の防水技術を把握するため、CIB W83/RILEM Joint Roofing Committeeの活動状況を報告する。
そのうえで、不具合のない防水工事を実現するための問題点や課題などを明確にし、学会仕様書・指針等関連する技術基準の今後のあり方や具体的な方向性について討論する。(日本建築学会大会資料より)
2014/07/28(月) 01:04:58|ニュース|